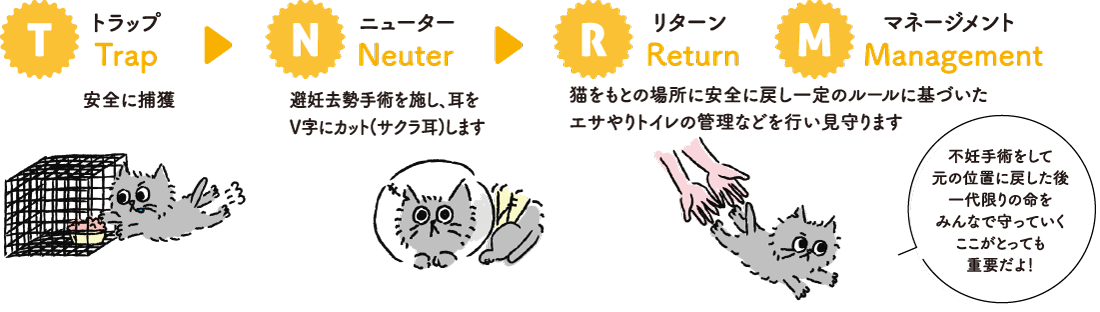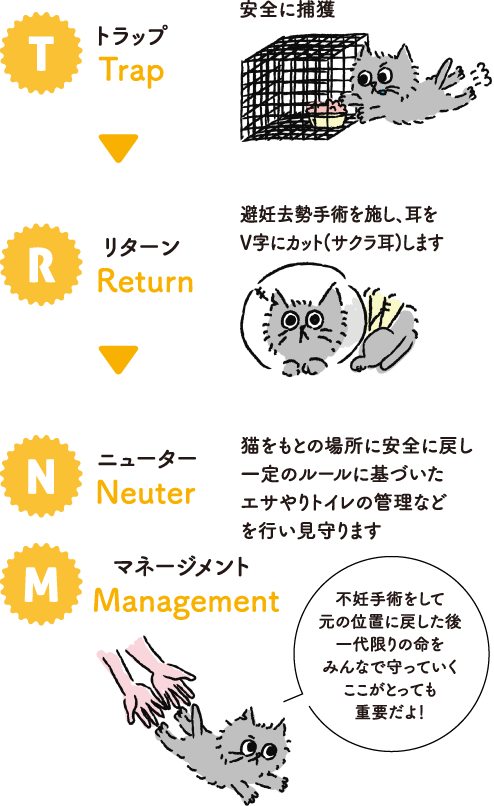人と猫が共存する
社会の実現、
野良猫から「地域猫」へ
一匹でも多くの飼い主のいない猫たちが、
人間から見守られ生きられるように、
人と猫が調和する環境の取り組み
「地域猫活動」を推進しています
地域猫とは?
地域住民の理解と合意が得られた上で、エサの管理や、ふん尿の処理、不妊・去勢手術措置、疾病予防対策等、その地域にあった方法で飼育管理する特定の飼い主のいない猫のことです。
地域猫活動とは?



飼い主のいない猫によるトラブルを、地域の環境問題として捉え、地域住民の合意のもと、ボランティア・地域住民が主体となり避妊去勢手術や一定のルールに基づいたエサやり、トイレの管理などを行います。
地域猫活動では、飼い主のいない猫を不要なものとして排除するのではなく、避妊去勢手術により一代限りの生を全うさせ、数年かけて地域から飼い主のいない猫がいなくなることを目指す活動。
地域猫活動の目的
地域住民と飼い主のいない猫との共生社会をめざし、飼い主のいない猫の不妊去勢手術を行う事で、不幸な子猫の増殖を防ぎ地域住民すべての理解、合意のもと、地域猫を見守る社会、環境マナーの向上に貢献していくことを目的としています。
地域猫活動はどうして必要なの?

猫の分類

-
飼主が明確であり、ご飯をもらい、完全室内飼で家族の一員として大事に管理されている猫
-
特定の飼主、お家、ご飯もなく、寒さ暑さ飢えに耐えながら地域に住み着き懸命に生きる猫
-
特定の飼主がなく、地域に住む人たちの合意とルールの下でご飯をもらい適正に管理されている猫
こんな効果が期待できます
- 不妊・去勢手術による効果
-
- 子猫が産まれなくなります。 (繁殖抑制)
- 尿のにおいがうすくなります。 (臭対策)
- 繁殖期による鳴き声がなくなる。 (鳴き声によるストレス解消)
- 行動範囲が狭くなります。 (被害範囲縮小)
- 地域の生活環境改善
-
- エサを与える時間や場所を定め、食べ残しを清掃することでカラスや鳩等の野生動物による餌の散乱による地域の美化を阻害することがなくなります。
- トイレを設置し、トイレの場所を覚えさせることで、ふん害が減ります。
- 住民トラブルや苦情の解消
-
- 繁殖を制限し、野良猫の数が減ることで、近隣トラブルの解消や苦情もなくなります。
- 地域猫活動がきっかけとなり、地域のコミュニケーションが活性化します。
- 地域で命を大切にする気持ちが生まれます。
地域猫活動は三者協働!

たくさんの猫がいる地域では、個人の力では解決が困難。しかし、地域の理解と協力のもとに行政・ボランティア団体三者協働で対策をすれば、着実に「飼い主のいない猫」の数は減少します。
これ以上「飼い主のいない不幸な猫」が生まれないようにするため、有効なのが「地域猫活動」 です。